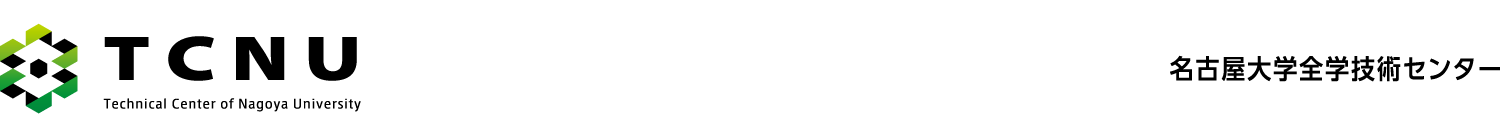技術職員ニュース
発行:統括技術センター広報担当 松浦
こんにちは! 統括技術センター広報担当の松浦です!
富士山の登山道が全て開通しましたね。
国土地理院のWEBサイトで標高を発表されている山は、1,003座。
その中でも標高が3,000メートル以上の山は23座で、3,500メートルを超えるのは富士山だけです。
私は、山は眺めるばかりという人間なため
何時間もかけて自分の体を何百、何千メートルと持ち上げ続ける登山家の体力と精神力には、畏敬の念すら覚えてしまいます。
ーーー・ーーー
今回は、名大計測・制御技術支援室の堀川さんにお話を伺いました。
堀川さんは名大の地震・火山研究センターにおられ、主に愛知県・岐阜県・長野県(御嶽山周辺)で約30箇所の地震観測点の保守作業を行っています。
観測点は、歴史的な経緯や大学の規模等で担当地域が決まり
頑丈そうに見える防水仕様の地震計であっても、環境によっては意外と壊れてしまうため保守作業はまめに行われるようです。
また、地震・火山研究センターでは、大きな地震があると教員・技術職員の所在確認が行われ、必要であれば招集されることもあります。
もし全国の大学・研究機関による合同観測班が設けられた場合は、基幹大学の指示に従い観測を行うそうです。
堀川さんは、過去、東北や熊本での大きな地震の際に招集された経験から
今年の初めに発生した能登半島地震の際は翌日から観測に出られるようにと、招集がかかる前にもかかわらず、自主的に準備と情報収集を始めたそうです。
とはいえ、能登方面の地理的知識がなかったため、まずは地名とその位置を覚えることから始め、それが一番大変だったとのこと。
そして、3月には東北大・金沢大が基幹大学となった合同観測班の一員として、余震観測に赴かれたそうです。
技術職員の方々の業務内容は、ほんとうに多岐に渡りますね。
取材させていただくたびに「そういう作業も存在するのね!」と驚いてしまいます。
知らないことに向き合う機会をいただけて、ありがたいです。
ーーー・ーーー
現在、名大博物館で展示されている「飛騨の自然」特別展では、堀川さんの使用されている観測機器やデータが展示されています!
機会があれば、ぜひ足を運んでみてください。
飛騨の自然-石と植物と人と-
https://www.num.nagoya-u.ac.jp/exhibitions/special/
冒頭でお話した山の標高については、こちらのサイトからご確認いただけます。
日本の主な山岳標高(国土交通省国土地理院)
https://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/kihonjohochousa41139.html
次回は、何の開放情報を共有できるでしょうか。
お楽しみに♪