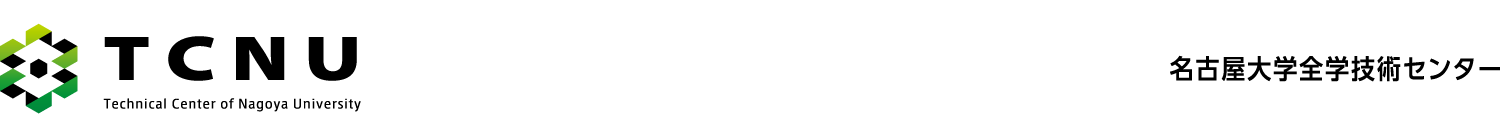技術職員ニュース
発行:統括技術センター広報担当 松浦
こんにちは! 統括技術センター広報担当の松浦です!
先週は、我が家の犬との近況に微笑んで下さる方がおられたようで、ありがとうございます。
犬を話題に持ち出すときは、たいてい話題に窮したときです。
過去に発行した技術職員ニュースの半分ほどが該当するような気がするのは、気のせいではありません。
ところで、沖縄はすでに梅雨入りしているそうですね。
以前、情報番組で「2024年の梅雨は、入りが遅く・期間は短く・雨量が多い」という予想を観た記憶があるのですが、どうなのでしょうか?!
やって来ないのは困るけど、長居されるのも悩ましい、それが梅雨…
ーーー・ーーー
さて今回は、名大分析・物質技術支援室の板倉さんを訪ねた時のお話です。
板倉さんは、医系研究棟の分析機器部門で電子顕微鏡の保守やユーザー講習、試料の作製(前処理)などを担当されています。
この日見せていただいたのは、透過電子顕微鏡(TEM)や走査電子顕微鏡(SEM)などの
顕微鏡の置いてあるお部屋のほか、顕微鏡で観察するための試料の前処理(試料作製)のお部屋でした。
電子顕微鏡で観察するためには、
電子線が何の引っ掛かりもなく透過できるよう試料をごく薄く切ったり、それをさらに固めたり、
電子線をムラなく当てられるように試料の表面をコーティング(蒸着)したりといった前処理が必要な時があります。
余談ですが、私はこの蒸着の装置が好きなため
板倉さんが案内してくださったお部屋の作業台に6台も並べてあるのを見たときに大変喜んでいました。
態度には出さず、うまく隠していたと思います。
話を戻して、、この、試料の前処理が適切でない場合や、試料に対して電子顕微鏡の加速電圧の数字が大きすぎる場合は
試料そのものへ大きなダメージを与えることになったり、撮像のゆがみや白飛びを引き起こしたりしてしまいます。
板倉さんは、まず観察したい試料の特性を理解し、そのうえで
形態を見るのに一番適した装置やその条件を考えるのだと教えてくださりました。
ひとえに'顕微鏡で観察する'といっても深い知識と経験が必要になってくるのですね。
ーーー・ーーー
統括技術センターWEBサイトでは、技術職員の皆さんの日々のご活躍を紹介しております。
新たに技術支援の記事を公開いたしました。
東郷フィールドにて、実習支援業務に取り組む技術職員の様子をお読みいただけます。
今後育つであろうブドウに思いを馳せながら、ぜひご覧ください。
フィールド実習支援「ブドウの花房のジベレリン処理」
https://www.tech.thers.ac.jp/20240531_field_gibberellin/
次回は、おそらく梅雨情報を共有できますね。
お楽しみに♪